皆さんは、先日行われた参議院選挙の投票には行きましたか?
私は期日前投票に行きました。
3連休の中日という事で投票率が下がるのではないかと言われていましたが、
少し高い投票率(58.51%)となったようですね。
今回の選挙で注目されていたテーマは、物価高対策や経済対策、減税といった生活に直結する分野です。もちろん、こうした課題への対応は、今まさに最も重視すべきポイントだと思います。
ただ、このブログをご覧の方は自衛隊やミリタリー、防衛政策に関心のある方が多いのではないでしょうか。
そこで今回はあえて「各政党の防衛や安全保障に関するスタンス」に注目し、比較してみたいと思います。
自衛官だった時から、自分の仕事に関係する分野だと思っていたので、一般的な人と比べると関心が高いとは思いますが、日々の生活に直結する問題の裏側で、防衛や外交の方向性をどう捉えるかも、選挙を考えるうえで見逃せない重要な視点だと思います。
自民党の安全保障政策
まずは自民党の防衛政策について見ていきます。
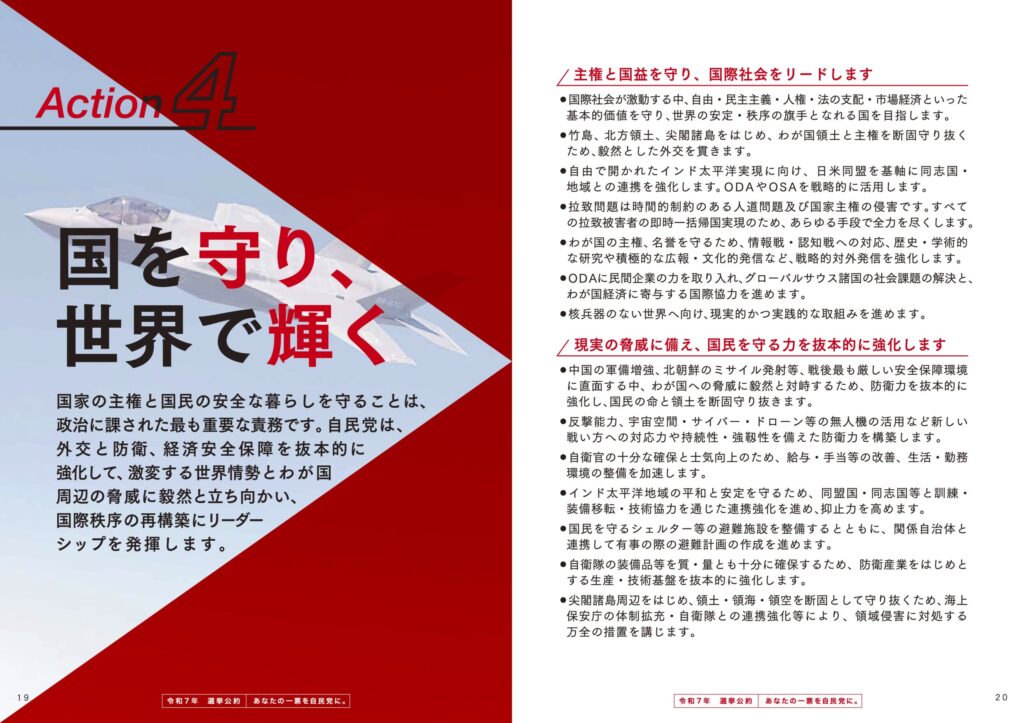
自民党は、「国を守り、世界で輝く」というスローガンのもと、外交・防衛・経済安全保障を一体的に強化し、日本の主権と国民の安全な暮らしを守ることを掲げています。特に、防衛政策については、現実の脅威に備えるため、防衛力の「抜本的強化」を明言しています。
具体的には、中国や北朝鮮といった周辺国の脅威を念頭に、反撃能力の保有や、宇宙・サイバー・ドローンなどの新領域への対応力強化を挙げています。また、持続性や強靭性を備えた防衛力の構築も重視されており、有事に備える体制を広範に整備しようという姿勢がうかがえます。
自衛官の人員確保や士気の向上にも力を入れており、給与や手当の改善、生活・勤務環境の整備も掲げています。
実際に陸自などの駐屯地では改築や営内(寮)へのエアコン設置が進んでいるようです。
さらに、海上保安庁との連携やシェルターなどの避難施設の整備など、国民保護にも配慮した政策が含まれています。
加えて、防衛産業の生産・技術基盤を抜本的に強化することで、装備品の質と量を確保し、持続可能な安全保障体制を構築しようという意図も見て取れます。
日米同盟を基軸に、同志国との連携強化や、ODA(政府開発援助)、OSA(政府安全保障援助)などの枠組みを通じて、自由で開かれたインド太平洋の実現を目指す姿勢も明確に打ち出されています。
最後に、竹島・尖閣・北方領土といった領土問題や、拉致問題への対応にも引き続き強硬かつ粘り強く取り組む方針が示されています。
自民党の防衛政策を読んでみて感じたのは、内容が「防衛三文書」と呼ばれる国の防衛方針とほぼ重なっているということです。
この三文書は、2022年に政府が改定したもので、「国家安全保障戦略」など、日本がどのように国を守るかを示した重要な方針です。
当時の政権は自民党だったため、自民党の政策と内容が一致しているのは自然なことだと思います。
立憲民主党の安全保障政策
次に、立憲民主党の防衛政策について見ていきましょう。
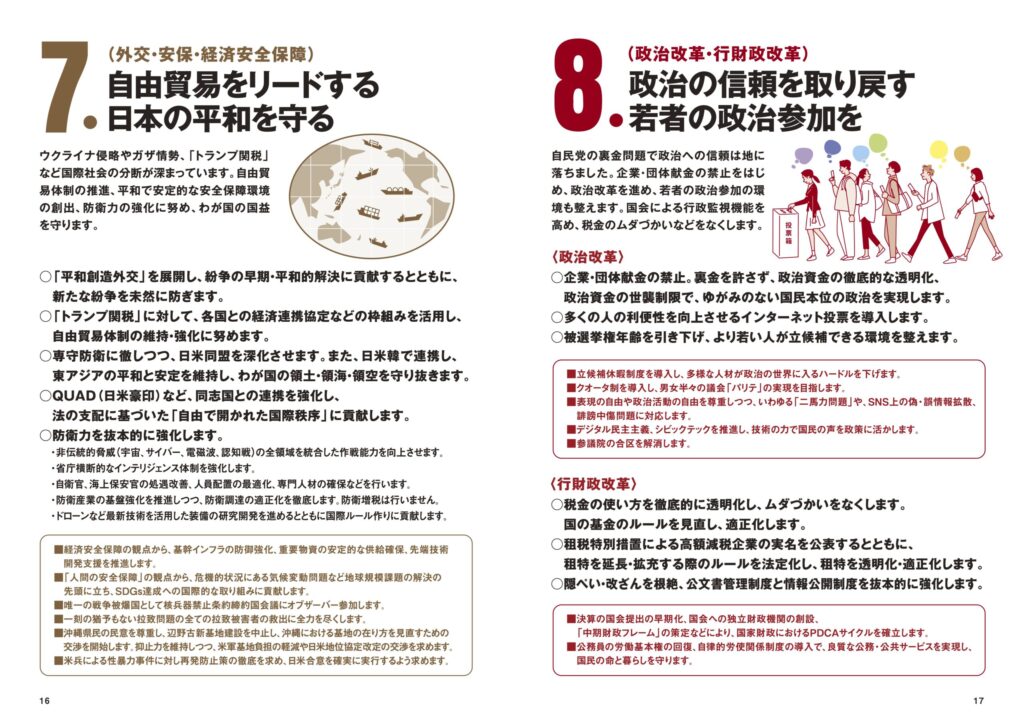
立憲民主党は、「平和で安定的な安全保障環境の創出」や「平和創造外交」の推進を掲げ、外交と防衛の両面から日本の安全保障を構築する姿勢を示しています。外交面では、紛争の早期解決と未然防止を目指し、日米同盟を深化させつつ、日中韓やASEAN+3、QUAD+などの多国間枠組みでの連携強化も重視しています。
防衛政策においては、「専守防衛」に基づきながらも、防衛力の抜本的強化を明言しています。宇宙・サイバー・電磁波・認知戦といった新たな脅威に対し、全領域を統合した作戦能力の向上を目指すほか、省庁横断のインテリジェンス体制の強化、自衛官や海上保安官の処遇改善、専門人材の確保にも取り組むとしています。
装備品に関しては、ドローンなど先端技術の研究開発を進めるとともに、防衛産業の基盤強化や防衛調達の適正化を重視しています。また、「防衛増税は行わない」と明記しており、財政とのバランスにも言及しています。
経済安全保障の面では、重要物資の安定供給やインフラ防御の強化、先端技術の開発支援を通じて、日本の戦略的自立を高める姿勢を示しています。また、非核三原則を堅持し、核兵器禁止条約の締約国会議にオブザーバー参加する方針も掲げています。
地域課題への対応としては、沖縄の民意を尊重し、辺野古新基地建設の中止を求め、米軍基地の負担軽減や日米地位協定の見直し、再発防止策の徹底を通じた安全確保を目指すとしています。
このように、立憲民主党は「平和的な外交の推進」と「現実的な防衛力の強化」の両立を目指した政策を打ち出しています。
公明党の安全保障政策
続いて、公明党の安全保障政策について見ていきましょう。

公明党は、2025年を「戦後・被爆・国連創設80年」という節目と捉え、「平和創出ビジョン」を掲げています。このビジョンの柱となっているのは「人間の安全保障」であり、国際社会が直面する地政学的対立や核の脅威、AIによる新たなリスクなどに対し、対話と協調を重視した安全保障戦略を提示しています。
具体的には、北東アジアにおける多国間の安全保障対話・協力機構の創設を日本が主導して推進する方針で、平和外交と国際秩序の維持を重視する立場を明確にしています。また、AIによる自律型致死兵器(LAWS)の開発に対しても国際的な規制を働きかけ、日本が議論を主導する姿勢を打ち出しています。
核兵器に対しては厳しく反対し、非核三原則の堅持を基本に、核兵器禁止条約の締約国会議へのオブザーバー参加や、核兵器国と非核兵器国の間の橋渡し役を果たすことで、核廃絶の実現を目指しています。
また、公明党は国際貢献にも力を入れており、地雷除去支援や国際保健(グローバルヘルス)への協力、気候変動への対応などを通じて、平和と人道支援の推進を掲げています。これらの取り組みは、SDGs(持続可能な開発目標)達成への加速化とも連動しており、ODA(政府開発援助)などを活用しながら、国内外の多様な主体と連携する方針です。
さらに、公明党は憲法に関して「加憲」の立場を取り、現行憲法の基本原則は維持しつつ、必要に応じて自衛隊の明記や統治機構への位置づけを検討するとしています。安全保障環境の厳しさが増す中でも、専守防衛を堅持しながら、外交努力と防衛力の整備の両輪で、日本の平和と安全を守る姿勢を打ち出しています。
日本維新の会の安全保障政策
続いて、日本維新の会の防衛政策を見ていきます。
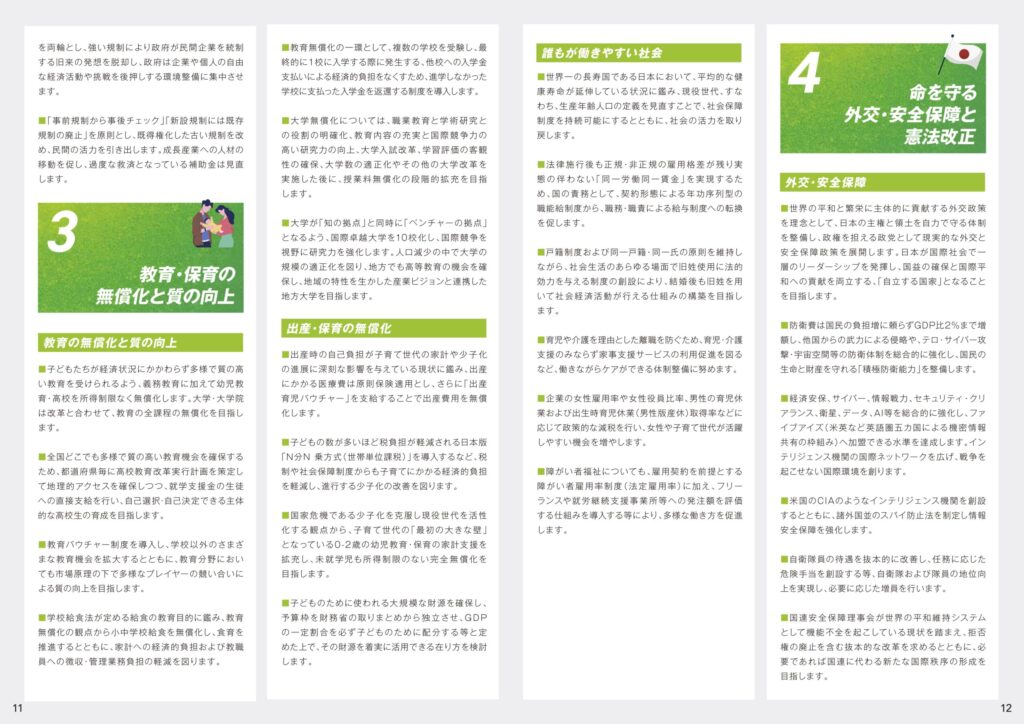
日本維新の会は、「命を守る外交・安全保障と憲法改正」を掲げ、日本が国際社会の中で主体的な役割を果たしつつ、自らの主権と領土を守る「自立する国家」を目指すとしています。防衛政策の中心には、「積極防衛能力」の整備が位置付けられており、他国からの侵略やテロ、サイバー攻撃、宇宙空間などの新たな領域に対する防衛体制を総合的に強化する方針を示しています。
防衛費については、国民の負担増に頼らず、GDP比2%まで引き上げると明記。サイバーやAI、衛星、情報戦力など、先端技術を活用した防衛力の強化を通じて、英米などのファイブアイズ(米英など英語圏五カ国による機密情報共有の枠組み)への加盟を視野に入れた水準を目指します。
さらに、アメリカのCIAのような専門的な情報機関の創設、スパイ防止法の制定など、情報安全保障の強化にも重点を置いています。インテリジェンス機能の強化により、戦争を未然に防ぐための国際環境の構築にも貢献するという考えです。
自衛隊については、任務に見合った危険手当の創設や処遇の改善を行い、必要に応じて人員の増員も検討するとしています。自衛隊およびその隊員の地位向上を重視し、現場での働きやすさを支える政策が示されています。
また、国連安全保障理事会が機能不全に陥っているとの認識のもと、拒否権の廃止を含む抜本的改革を求めるとともに、必要であれば新たな国際秩序の形成にも取り組むとしています。日本人を国際機関のトップに送り出すことで、日本の国際的プレゼンス向上を図る方針も明記されています。
外交面では、人権や法の支配といった普遍的価値を共有する国々との連携を強め、国際司法裁判所の積極活用による平和的解決を重視。さらに、経済安全保障の観点からサプライチェーンの多角化やエネルギー・食料の自給率向上などにも取り組み、日本全体の安全保障基盤の強化を図っています。
日本共産党の安全保障政策
共産党は、「戦争をさせない日本」を掲げ、憲法9条を生かした平和外交の推進を中心に据えています。最大の特徴は、自衛隊の解消を最終的な目標とする立場を取っていることです。これは一貫した理念に基づくもので、当面は憲法に反するとしている安保法制や敵基地攻撃能力の保有に明確に反対しています。
外交面では、対話と協調による平和的解決を重視し、日米安保条約の廃棄を訴えています。代わりに、日本が軍事同盟に依存せず、ASEAN諸国などとの平和的・多国間の地域安全保障体制の構築を模索する姿勢を示しています。また、米軍基地の整理・縮小・撤去を進め、特に沖縄の基地負担軽減を強く主張しています。
防衛費の大幅な増額には強く反対し、「軍拡路線」は日本の安全をかえって危うくするとしています。代わりに、気候変動、感染症、災害対策など「人間の安全保障」こそが現代の安全保障の中心であると提案しています。
核兵器廃絶にも積極的で、日本政府に対し核兵器禁止条約への署名・批准を強く求めています。被爆国としての立場から、核抑止力に依存する安全保障政策に対しては根本的な見直しを訴えています。
自衛隊の問題に関しては、段階的に自衛隊を解消し、憲法9条の完全実現を目指すと明言しています。ただし、現状では災害対応などで自衛隊が果たす役割もあるとして、直ちに全廃するという立場ではありません。国民的合意を得ながら、非軍事の安全保障体制へと移行することを目指しています。
このように、共産党の安全保障政策は他の主要政党と比べても大きく異なる理念に基づいており、軍事力による抑止ではなく、憲法と国際協調による平和構築に軸足を置いた政策が特徴です。
国民民主党の安全保障政策
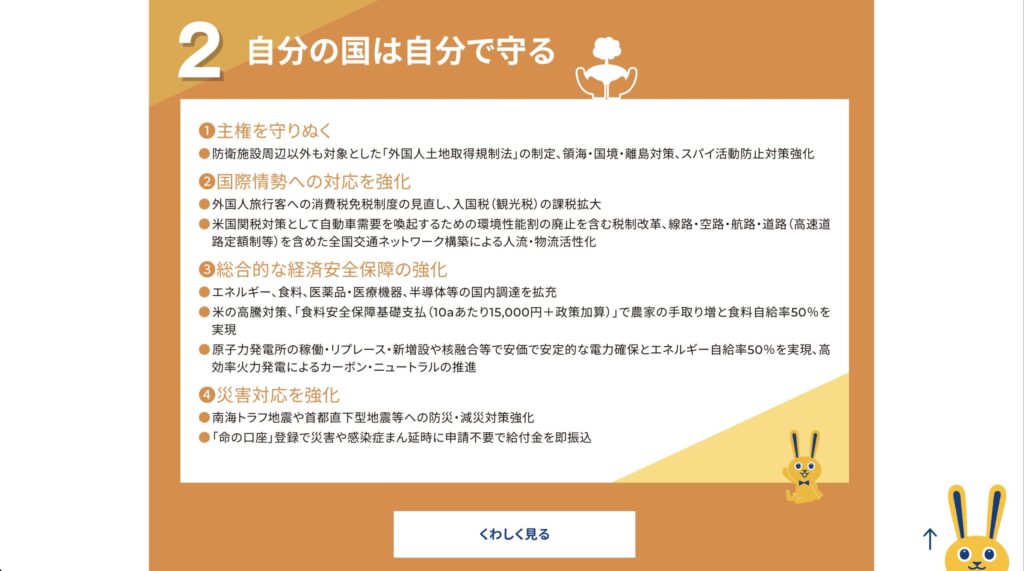
国民民主党は、「自分の国は自分で守る」という方針のもと、経済・エネルギー・食料・防衛などを含めた総合的な安全保障の強化を掲げています。その根底にある理念は「現実的平和主義」。これに基づき、「近くは現実的に、遠くは抑制的に、人道支援は積極的に」という原則を安全保障の基本方針としています。
防衛政策においては、「専守防衛の堅持」を明言しつつも、現代の脅威に対応するため「自衛のための打撃力」、いわゆる反撃能力の保持を主張しています。これは抑止力の一環として位置づけられており、日本の領土・領海・国民の生命と財産を守るための対応としています。
また、サイバー分野では「アクティブ・サイバー・ディフェンス(ACD)」を導入し、平時から攻撃者の動向を把握して迅速に対応する体制を整備する方針です。このために「サイバー安全保障基本法(仮称)」の制定も目指しています。
日米同盟については重視する姿勢をとりつつ、「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」の見直しや、日米地位協定の改定も主張しており、日本の自立的な防衛体制の構築を進めたいという姿勢が見られます。
装備面ではミサイル防衛体制の強化として、現在開発中のイージスシステム搭載艦の有効性を検証する一方、中止が決定されたイージス・アショアの再検討も視野に入れています。また、国民保護の観点から地下シェルターの設置推進も提案しています。
さらに、自衛官の処遇改善にも力を入れており、勤務環境の向上、留守家族支援、女性自衛官の支援、退職後の再就職など、人的基盤の強化にも積極的です。
防衛装備の国産化や技術基盤の整備についても明記されており、国内の防衛産業を支援することで、「自分の国は自分で守る」ための現実的な体制強化を目指しています
このように、国民民主党は専守防衛を堅持しながらも、現実的かつ多面的な視点から防衛力の整備や経済・技術・人材面の強化を進めることに重点を置いています。
れいわ新選組の安全保障政策
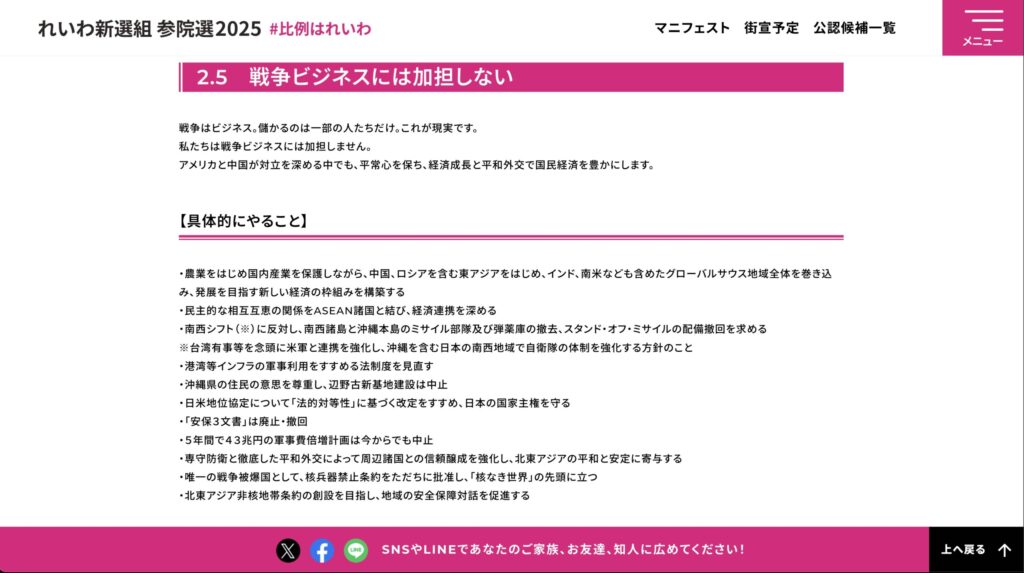
れいわ新選組は「戦争ビジネスには加担しない」という理念のもと、軍拡ではなく平和的手段を重視した安全保障政策を掲げています。党の基本姿勢は、軍事力による抑止ではなく、経済成長と平和外交によって国を守るという考え方です。
れいわは、政府が進める防衛費の大幅な増額、いわゆる「5年間で43兆円」の計画に反対し、防衛3文書の撤回を求めています。また、南西諸島や沖縄本島へのミサイル配備を含む「南西シフト」にも反対し、住民の意思を尊重した防衛政策を提案しています。日米地位協定についても、法的対等性に基づいた改定を主張し、米軍との関係を見直す姿勢を示しています。
軍備強化の代替としては、国内産業の振興やエネルギーの自給率向上を通じた安全保障の確保を目指します。たとえば、原発の即時廃止と再生可能エネルギーへの投資による地域雇用の創出を掲げており、これを「グリーン・ニューディール」と呼び、10年間で200兆円の投資と250万人の雇用創出を計画しています。
さらに、農業・食料自給率の向上や種子法の復活など、経済・食料・エネルギーの自立を安全保障の一環として捉えているのが特徴です。また、ASEAN諸国やグローバルサウスとの経済協力を重視し、相互利益に基づく新たな経済圏の構築を目指しています。
外交面では、専守防衛を堅持し、徹底した平和外交の推進を掲げるとともに、核兵器禁止条約の批准を求め、「核なき世界」の実現を訴えています。北東アジア非核地帯条約の創設にも意欲を示しており、唯一の被爆国として積極的な役割を果たす姿勢を明確にしています。
社会民主党の安全保障政策
社会民主党は、憲法9条を中心とする「平和主義」を最も重視する政党です。近年の防衛政策の転換、特に安倍政権以降の防衛力強化や安保法制に対して、強く反対の立場をとっています。社民党は、軍事的手段ではなく、非軍事・人道的手段による安全保障の実現を訴えています。
まず、防衛費の大幅増額や敵基地攻撃能力の保有については、平和憲法の理念に反するとして反対を表明。特に、政府が閣議決定のみでこうした方針を進める姿勢に対しては、民主主義の手続きを無視していると批判しています。
また、核兵器に関しては、核抑止力に頼らない姿勢を明確に示し、非核三原則の法制化や核兵器禁止条約への批准を強く求めています。核兵器の先制不使用を求めるなど、核廃絶に向けた国際的な取り組みを重視しています。
米軍基地問題では、特に沖縄の基地負担に注目し、辺野古新基地建設の中止、普天間基地の撤去、在沖米軍の縮小・撤退などを主張。思いやり予算や米軍再編交付金にも反対しています。
さらに、日米安保条約については、将来的に平和友好条約への転換を目指すとし、軍事同盟依存から多国間協調型の安全保障体制への移行を提案。北東アジアの非核地帯化や集団安全保障の枠組みづくりも目標に掲げています。
そして、自衛隊については専守防衛に徹するよう活動を限定し、長距離ミサイルや攻撃型装備の保有には反対。防衛費の透明化や文民統制の徹底、情報公開の強化を求めています。
このように社会民主党は、軍事によらない「人間の安全保障」の実現を軸にした平和志向の政策を展開しています。
参政党の安全保障政策
参政党は、安全保障を「防衛・外交・経済・情報・文化」の5つの分野で支える“総合力”として捉え、あらゆる角度から日本を守る体制の構築を掲げています。現代の国際社会では、軍事だけでなく、メディアによる世論操作や経済的な圧力、サイバー攻撃なども含めた「超限戦」と呼ばれる新たな形の戦いが進行しています。参政党は、こうした目に見えにくい攻撃にも先手で備えることが必要だと主張しています。
防衛の基本方針としては、「①日本独自の防衛力」「②対等な日米同盟」「③国際連携」の3本柱を提示。核保有国に囲まれた日本の現実を踏まえた上で、核廃絶を目指しながらも、抑止力の維持が必要だとしています。
また、偽情報やサイバー攻撃に対応するために、情報機関の強化、日本版スパイ防止法の制定、そして正しい情報を国際社会へ発信する「カウンタープロパガンダ」の実施も訴えています。国民が偽情報に騙されないよう、情報リテラシー教育の推進にも力を入れています。
さらに、外国からの「静かな浸透」――いわゆるサイレント・インベージョンへの対策も重要視しています。外国人の受け入れ制限や、土地・水源・離島などの買収規制を強化し、特に重要な国土や資源が他国に握られないようにする方針です。
その一環として「外国人総合政策庁」の設立を提案し、外国人受け入れに関する制度を一元的に管理する体制の構築を目指しています。労働市場や社会保障、永住・帰化に関する条件の厳格化、公務員採用や土地売買の制限など、幅広い分野で国益を守るための制度見直しを掲げています。
外交面では、日本の伝統的な価値観を活かし、自由や民主主義を守る国家としてのリーダーシップを国際社会で発揮することを目指しています。
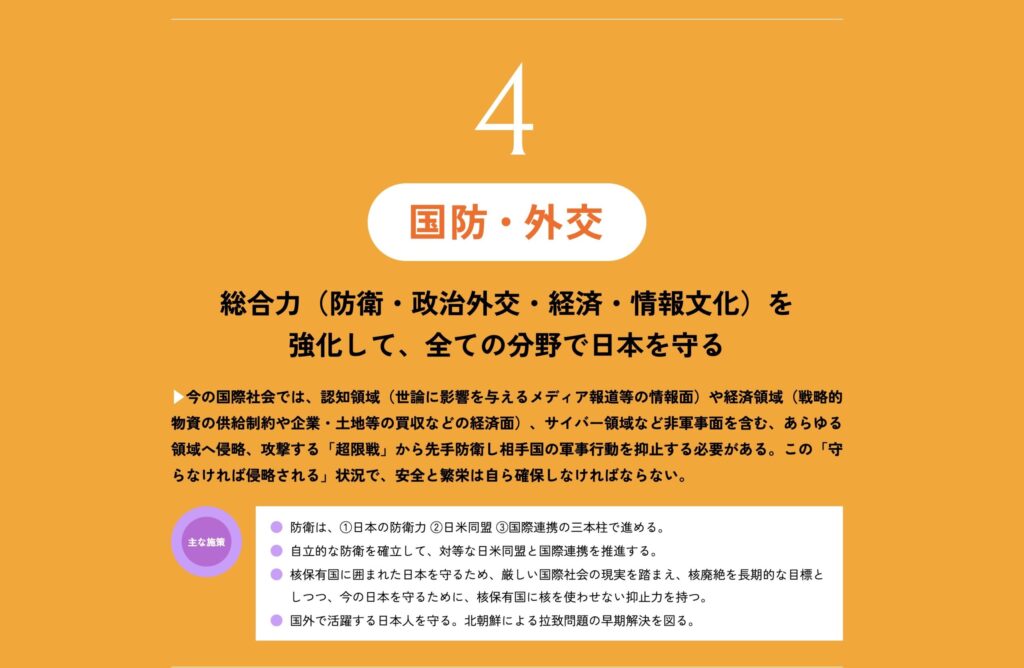
日本保守党の安全保障政策
日本保守党は、「自衛のための力を明記する憲法改正」を柱に、安全保障体制の強化を掲げています。具体的には、憲法9条第2項の「戦力不保持」条文を削除し、自衛のための実力組織の保持を明文化することを目指します。併せて、自衛隊法を改正し、自衛隊の名称をよりふさわしいものへ変更。また、在外邦人や日本に協力する外国人の救出を可能とする法整備も進める方針です。
さらに、海上保安庁法の改正により、他国のコーストガードと同等の対処力を持たせ、尖閣諸島周辺などの警備力を強化するとしています。
情報安全保障の面では、「スパイ防止法」の制定と、諜報専門機関の設置を提唱。諜報活動への対応力を高め、日本の安全保障に直結する情報体制を強化します。
防衛産業に対しては、研究助成や政府投資を促進し、国内での装備開発・供給能力を高めることにより、自主防衛体制の強化を図ります。
また、安全保障上の懸念から、外国勢力による不動産、特に土地の買収については禁止とする法整備を進め、日本の国土と主権を守るとしています。
まとめ
各政党の安全保障政策を比較してみて、改めてそれぞれの特徴の違いがよく分かりました。
中には、安全保障分野に関して詳細なPDF資料を公開している政党もあれば、過去の政策を否定するだけで具体的な提案が見えにくい政党もあり、その姿勢の違いが興味深く感じられました。また、公式サイトの構成にも違いがあり、イラストや図表で視覚的に分かりやすく伝えようとしている政党もあれば、文字情報だけで構成されているところもあります。
これまで自分は、投票権のある選挙にはすべて参加してきましたが、候補者や政党の考え方をどこまで深く理解できていたかとなると、正直なところ自信はありません。
しかし、今回のように自分で各政党の公式サイトを見比べてみるだけでも、得られる情報は多く、発見もありました。
今ではSNSやネットを通じて手軽に情報を得られる時代ですが、自分自身で一次情報にあたることの大切さを、今回改めて実感しました。


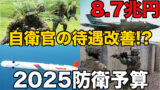


コメント